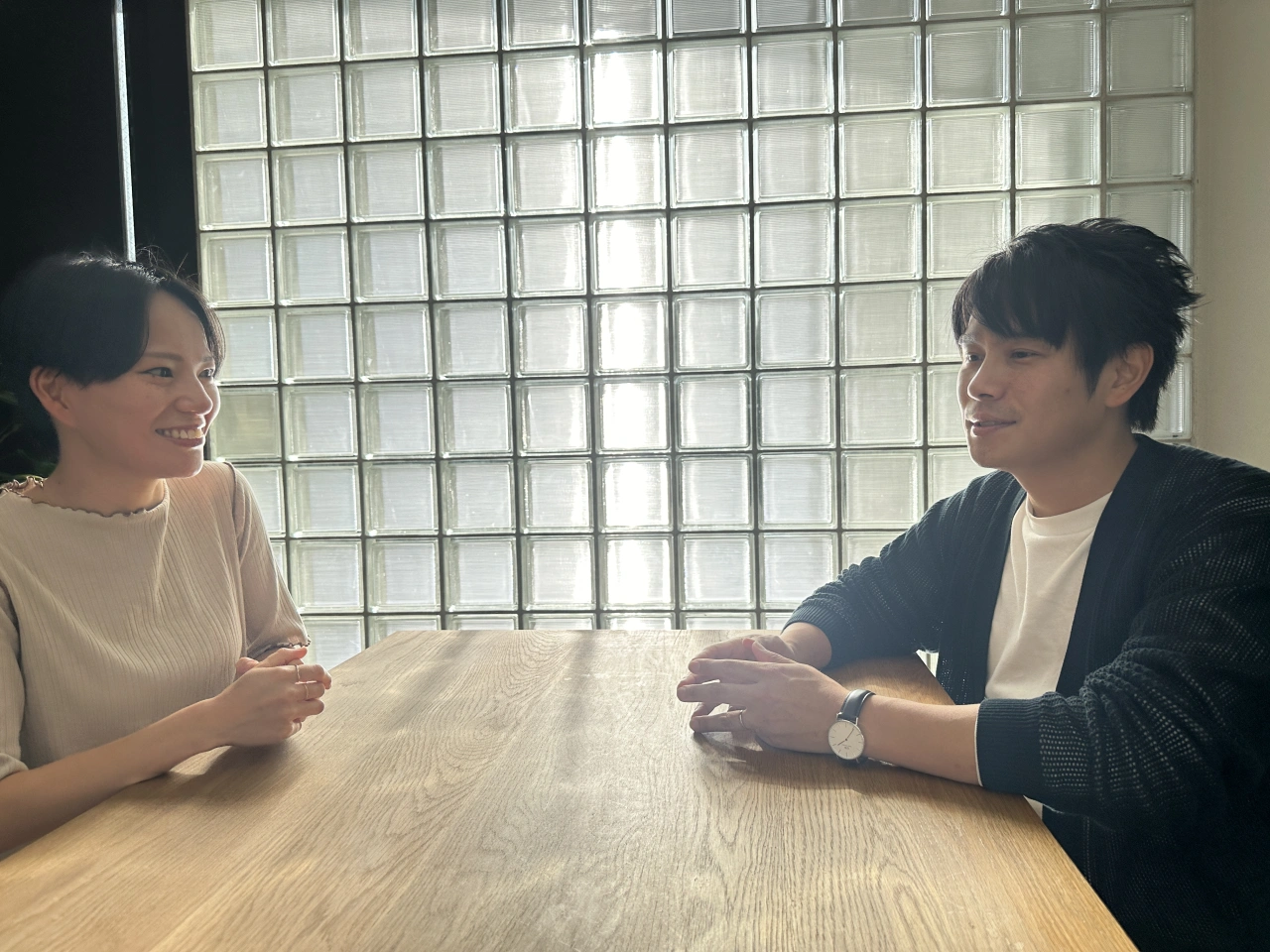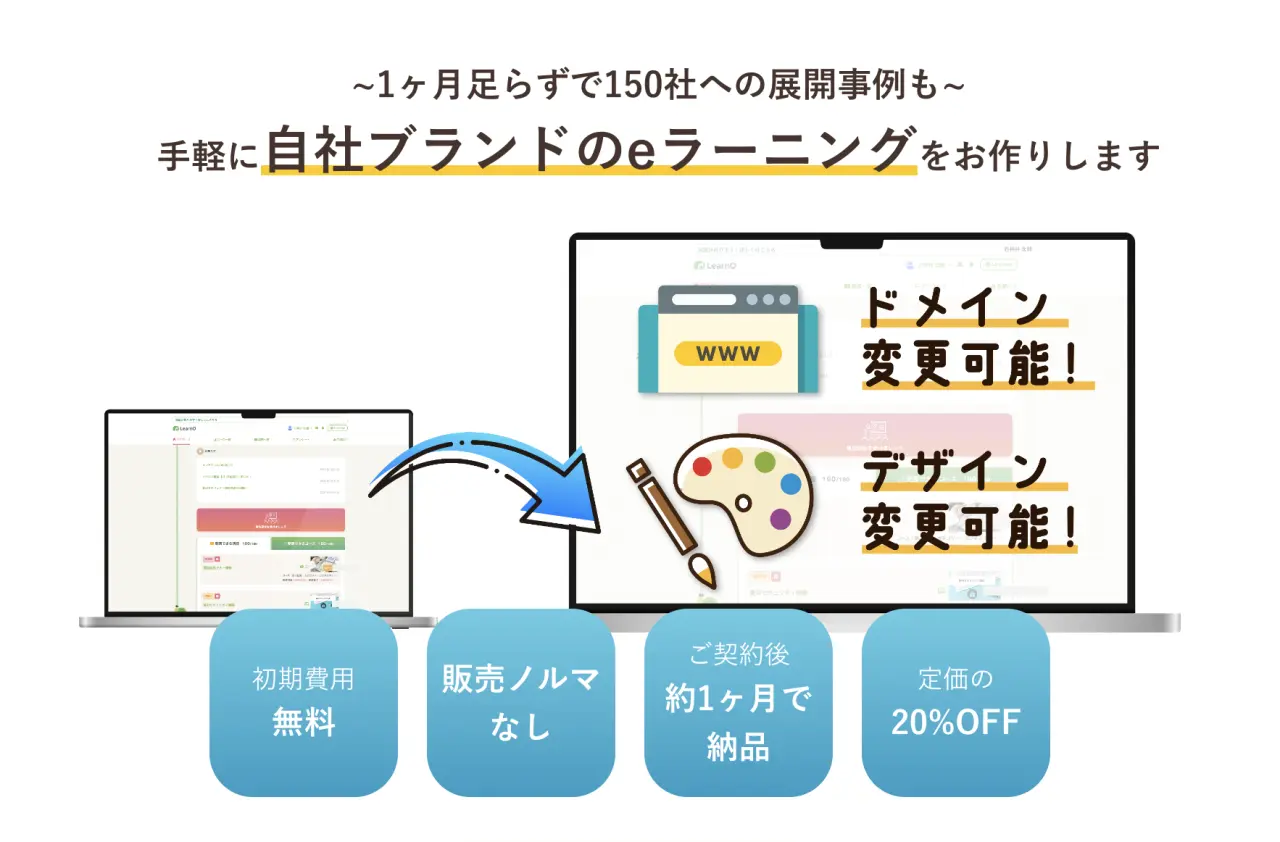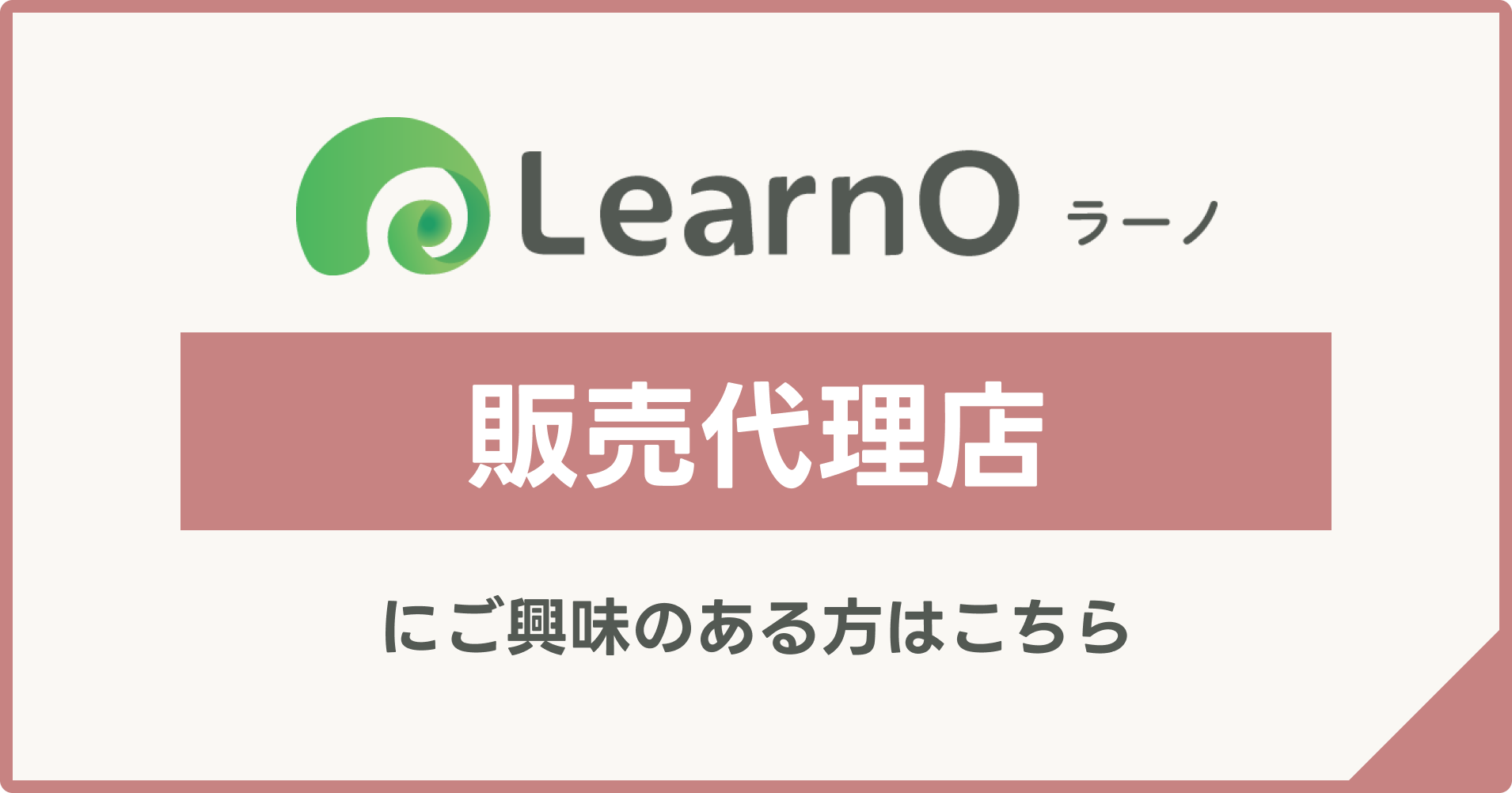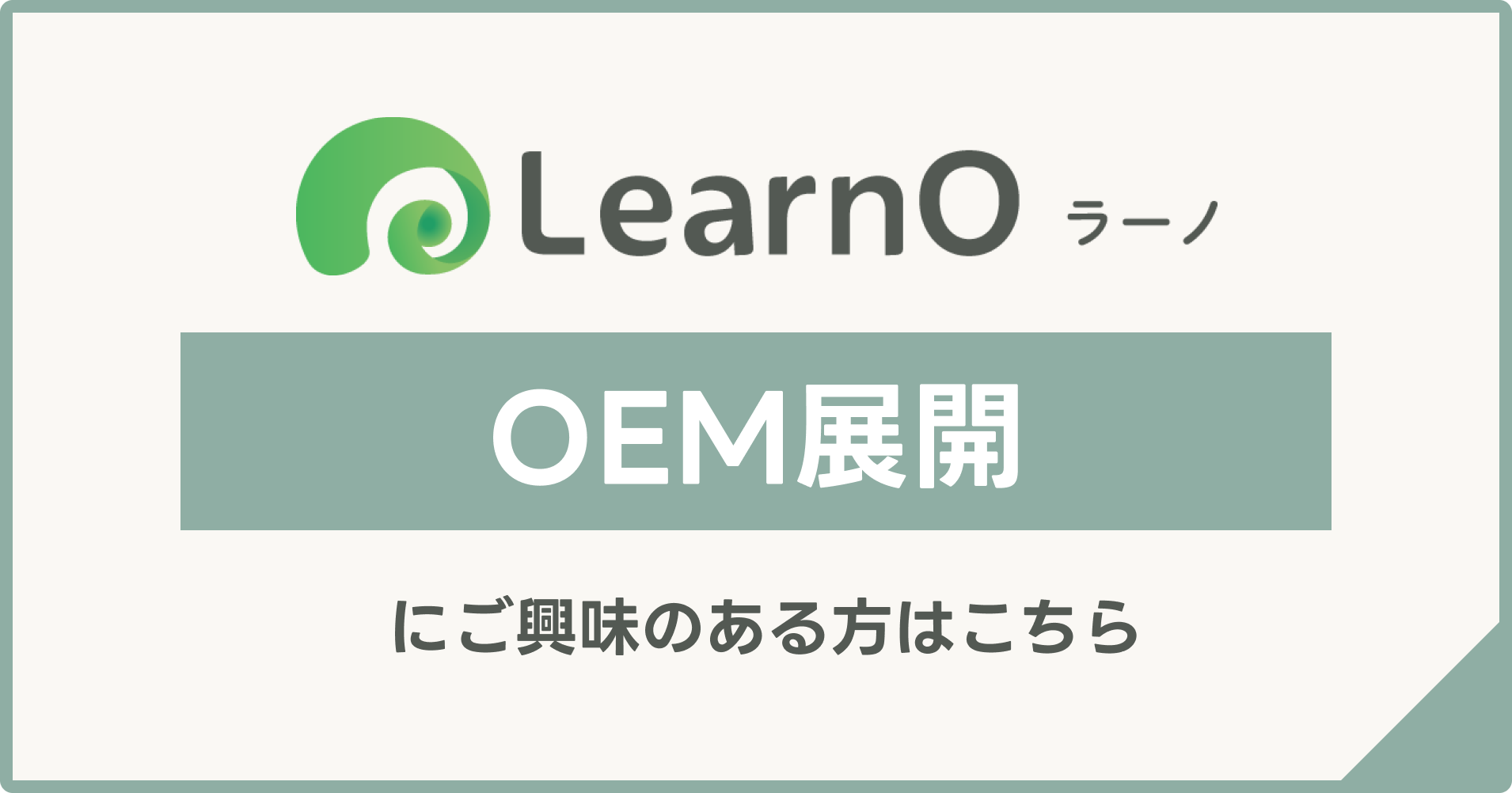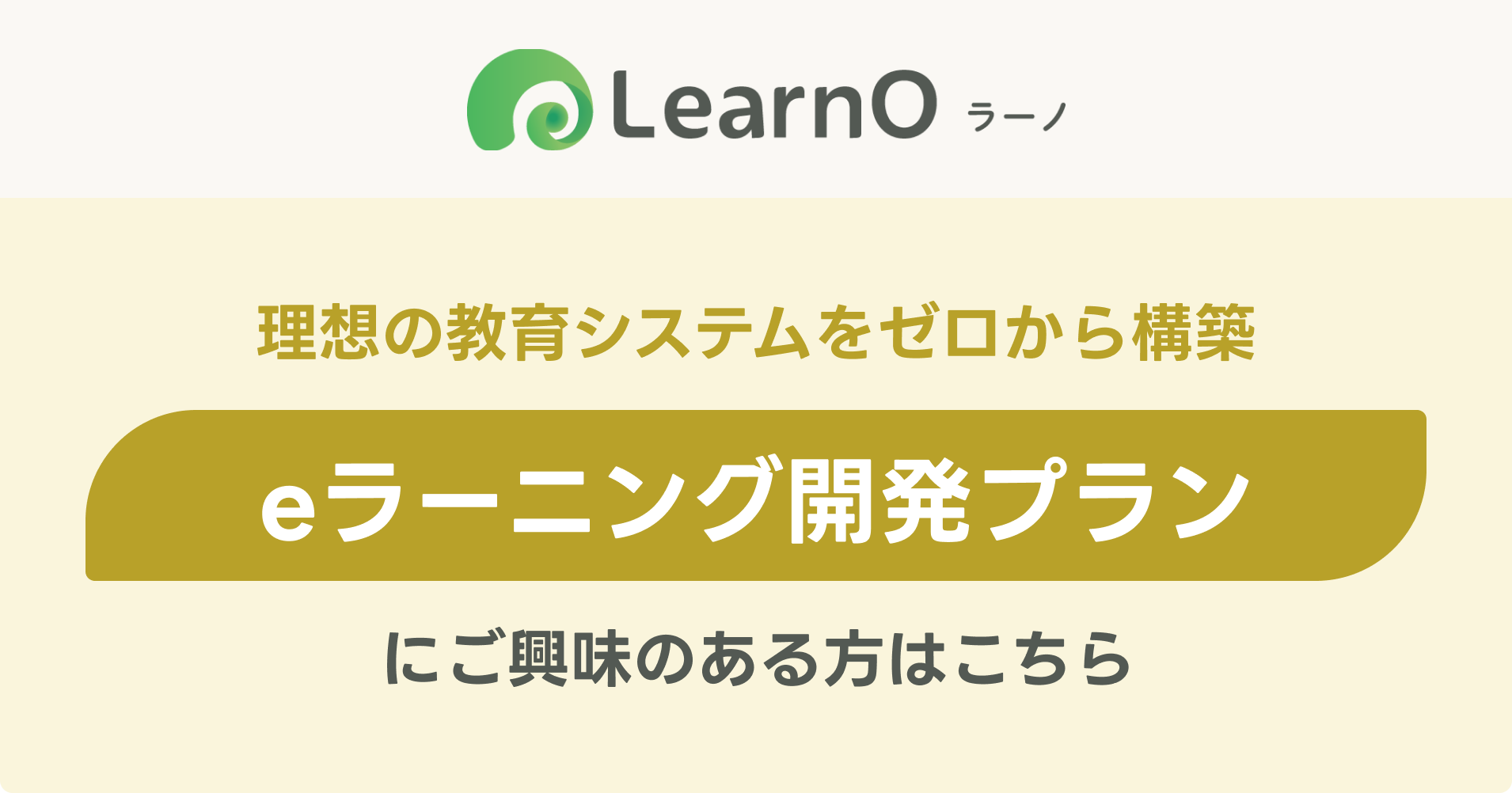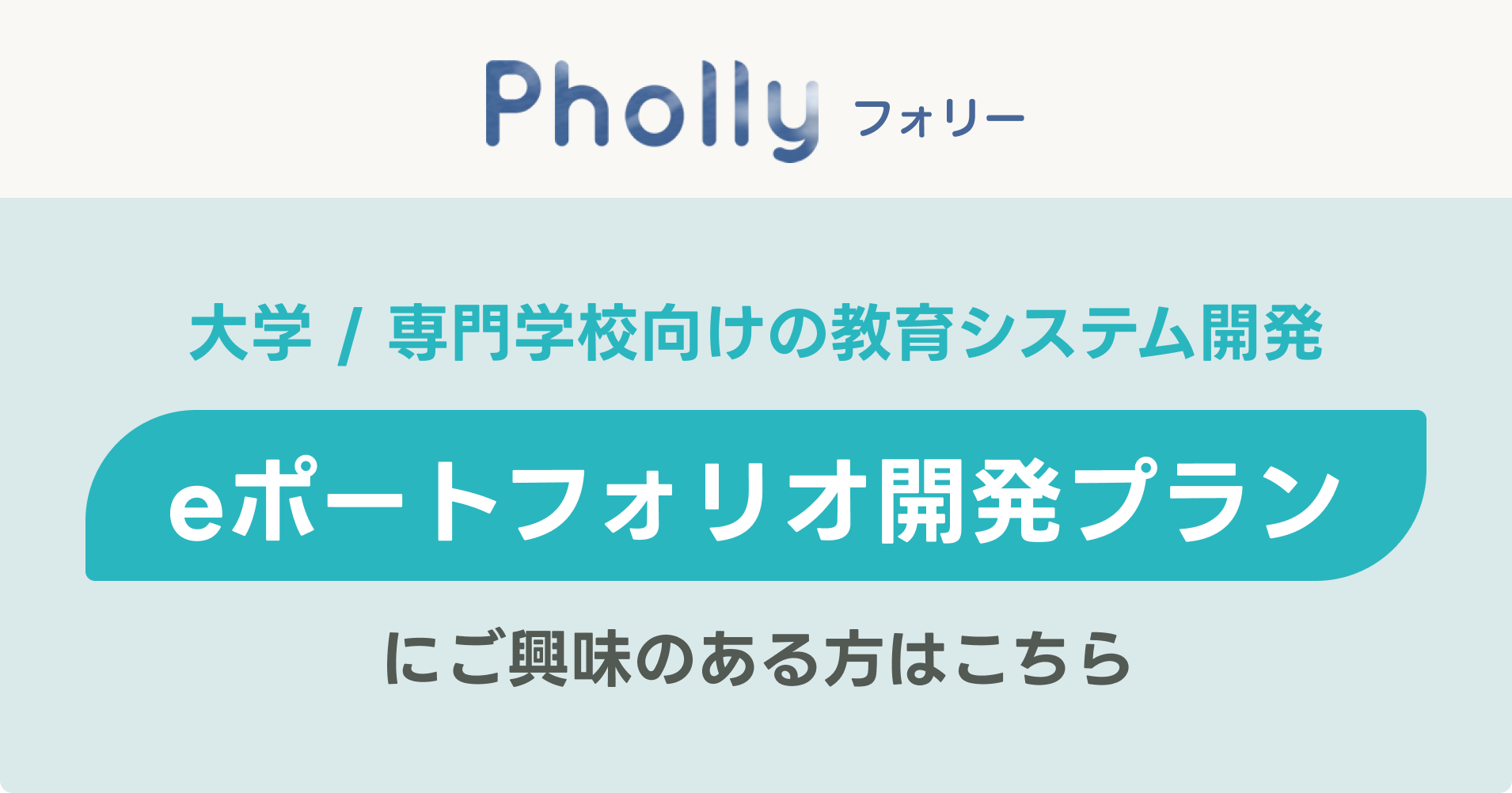このシリーズでは、全3回かけてサービス・マーケティング部門のお二人にお話を伺います。第2回目は、要件定義から開発まで、プロジェクトの具体的な流れについてお話をお聞きします。
今回の対談者

サービス・マーケティングの市村です。マーケティング業務や、システム開発プロジェクトのディレクションを担当する部門のチーフです。
同じくサービス・マーケティングの村越です。お客様にご満足いただけるよう、日々奔走しています。
サービス・オペレーションの瀬尾です。eラーニングシステムLearnOが全然売れていないときから試行錯誤を繰り返し、3,800社に利用されるサービスへと成長させました。
予算に合わせたフェーズ分けで、最適なシステムをご提案
瀬尾
今回は、カスタムメイド開発の具体的な流れについてお伺いします。プロジェクトの最初の段階では、クライアントが社内で困っていることを洗い出していくと思います。しかし、話し合ううちに「あれもやりたい、これもやりたい」と盛り込みたい機能が増えてしまい、当初の予算や目的から外れてしまうことはないのでしょうか?
市村
なるほど。クライアントが困りごとを解決するために当初用意していた予算と、ヒアリングしたのちにこちらが提案する規模や金額がズレたりする場合ですよね。やはり、クライアントはシステム側が見えにくいのでどうしても、予算を少なめに見積りがちです。だからといって、予算にあわせて無理やり詰め込んでもいいものができません。
そのような場合は、予算に応じたフェーズ分けを提案しています。「今回の予算ではここまで可能です。ここまででもこういう効果が見込めます。大きく作るより、小さく作って現場に入れてフィードバックをもらいながら作る方がいいことがあります」などとお伝えすることで、実現したいことと予算感のバランスを取っていくのです。
瀬尾
そのあたりの調整は具体的にどこで行われるのでしょうか?
村越
まずクライアントへのヒアリングのち、社内で検討して要件定義前の概算お見積としてお出しします。そして、次に詳しく要件を定義していったのち、最終的なお見積の金額だったり、フェーズ分けをご提案していく流れです。

クライアントとの綿密なコミュニケーションで、納得感のあるシステム開発を実現
瀬尾
では、要件定義を進めていくとディレクターとしてはちょっとハラハラすることがあるんじゃないでしょうか?ここまでやると概算お見積より高くなりそうだなとか。
村越
要件定義が終わってから全てをお伝えすると驚かれますから、打ち合わせの中で明らかにシステムの工数が増えそうなものは随時お話しさせていただいています。
瀬尾
要件定義の期間はクライアントにとっても、Mogicにとっても具体化が進む分、ちょっと意外な展開がありそうでドキドキしますね。それでは、要件定義は通常どのぐらいで終わるものでしょうか?
村越
サービスの規模によりますが、およそ1-2ヶ月です。すごく大規模な開発でも3ヶ月にまとめています。
瀬尾
要件定義の打ち合わせの頻度はどのぐらいですか?
市村
規模が大きい場合は週に1回ほど行いますが、通常は隔週に1回ほどです。もちろん打ち合わせと打ち合わせの間に、クライアントでも整理や確認事項がありますし、Mogicでもシステムやデザインの詰めを行いますから。基本はクライアントの負荷にならないようなスケジュールを組みます。
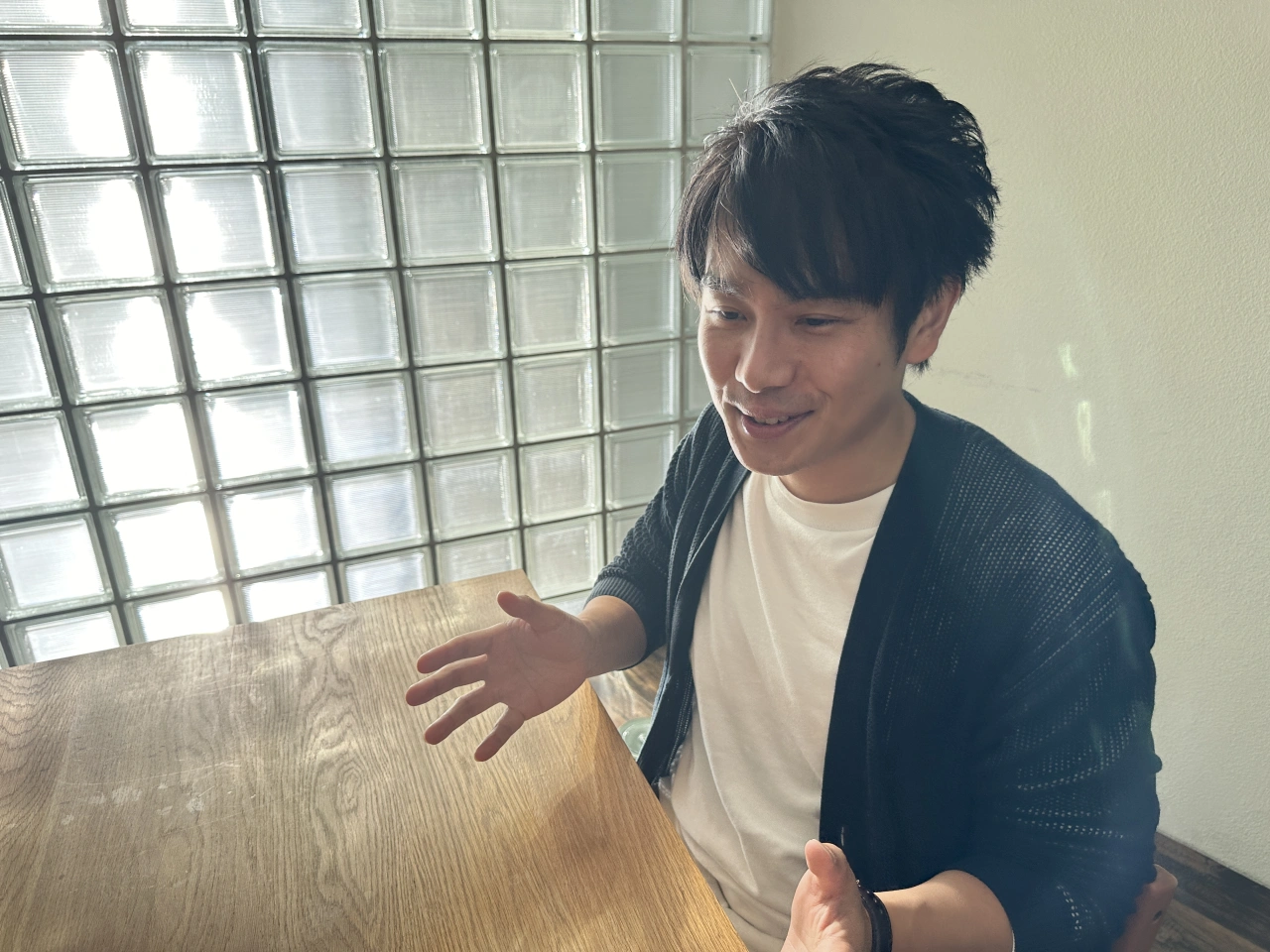
瀬尾
要件定義を進めた結果、クライアントが違うと思ったらそこで止めることはできるのでしょうか?要件を詰めていくなかで出てきた条件がどうしてもクリティカルでクリアできないなどあるのかなと。
市村
そもそも要件定義に入る前に「最終的にはこういうサービスになります」という提案書を書いていますので、これまで要件定義の後で止まったということはないですね。ですが、クライアントの意向で止めることはできます。
課題を徹底的にあぶり出し、最適なアプローチを模索
瀬尾
これまで要件定義で印象的なケースはありましたか?
村越
つい最近リリースした案件でありました。クライアントの中で業務上の課題は分かっているけど、どういう解決策がいいかがまったく想像つかないという話でした。
ですから要件定義をしていく中で、課題を洗い出して優先順位づけをして、思いつく解決策のうち期間や予算、今後の改修コストを総合的に考えて最適なものを一緒に選んでいきました。
結果としてリリースしたのち、「もともと解決したかった課題がすごく改善されました。いいサービスになりました」とコメントいただきまして、すごく印象に残りました。
瀬尾
試行錯誤していく要件定義は難しかったですか?
村越
クライアントは運用の課題が分かっているけど、ITの知見が少ない。Mogicには、過去の事例やITの知見はあるけれど、運用の状況が分からないという状況でした。お互い持っている情報が違うのでそこを擦り合わせて相談していくのが難しかったかなと思います。
瀬尾
ヒアリングする回数が増えたのではないでしょうか?
市村
要件定義の前にもリスト化した改善点をいただいて、打ち合わせでもヒアリングを重ねて、それでもうまくつかめないところがありましたから、個別にお電話したり、オンラインミーティングをさせていただきました。もうくりかえし、くりかえしお聞きするという感じです。
瀬尾
執念といいますか、課題を突き詰めていくところがすごいですね。
開発段階でも社内外とのコミュニケーションを徹底
瀬尾
要件定義が終わり、金額や期間が固まったら次は何をするのでしょうか?
市村
次は、デザイナーによるデザイン制作です。そこまでにワイヤーフレームというサイトの骨格は合意できているので、デザイナーはウェブデザインとして色味や操作性のイメージがつくものを作っていきます。それと同時にエンジニアはシステム設計を進めて、実際にプログラムを書いていく形になります。
瀬尾
そうなるとディレクターとしてはデザイナーやエンジニアにお任せしていて待機しているのでしょうか?
村越
確かに見守っている状態ではあるのですが、やはり一番要件を把握しているのはディレクターなので、デザイナーやエンジニアと定期的にコミュニケーションしながら仕上がりを管理しています。進捗や課題を適時クライアントにフィードバックしていることもあります。

今回は要件定義から開発までの具体的な流れについて伺いました。次回は、最終テストから運用までの流れと、プロジェクトに臨む姿勢についてお話をお聞きします。
次回の記事はこちら